この記事の要約
- ITサービスは、収益化するのが実は難しいモデル
- 企業として運用すると、どうしても固定費がかさむ
- どんどん開発や運用は簡単になってきており、十分個人でも運用できる時代
- 個人として運用して、安価な料金体系でも利益を出せる仕組みがベスト!?
ITサービスの収益モデル
ITサービスの収益モデルにはいくつかのタイプがあります。
- 月額課金を設定する
- 広告を貼り付けて広告収入を得る
多くのサービスは無料の枠があり、そこには広告収入が貼り付けられ、サービスのすべての機能を使うためには、月額課金をして広告もなくなるというモデルが多いです。
日本のサービスで言いますと、Chatwork、freeeなども、似たような料金体系をとっています。
サービスを継続するにあたっての問題
これらのサービスを継続するにあたって、料金設定をするときに、どのような問題が起きるのでしょうか。
それは、ズバリ価格競争です。
ITサービスは、特に仕組みが簡単ですと、すぐに真似をされてしまいます。いい例が中国版Youtubeの「优酷(Youku)」など、中国版○○を沢山開発しているということです。
それでは研究開発をして他社が真似をできないようにすればいいではないか、というとそれもすぐに限界が訪れます。
実際のモノがあるわけではないので、ある機能を追加してもそれもすぐに真似をされて、最終的には開発した機能を更に良くしたものを開発されて。。。というイタチごっこが繰り返されます。
そして、ITサービスは最終的に価格競争になり、採算が合わなくなった企業は撤退を余儀なくされます。
どのようにITサービス企業は生き残っているのか
ITサービスを組織だって開発していくと、必ず上記のような問題に立ちふさがります。
原因は後述しますが、この原則から逃れることは非常に難しく、IT企業は価格競争の中で戦い続ける必要があるでしょう。
それでも、多くのIT企業がどんどん生まれて、どんどん新しいサービスを作っていっています。
それらの企業はどのように勝ち残っているのでしょうか?
方法は大きく3つあります。
1つ目は、次々とサービスを生み出し続ける方法です。
1つ1つのサービスには必ず終わりが来るということを認識した上で、どんどんとサービスを生み出し続ける方法です。
Googleなどは、この方法でどんどんサービスを開発し続け、採算が合わなくなったサービスはどんどん撤退していっています。
日本では、リクルートなどもこの方法でサービスを作っては壊し、を続けていますね。
2つ目は、ものすごい勢いでサービスを進化させ、顧客を一気に取り囲んでしまう方法です。
LINEなどはこの方法で一気に顧客を取り囲みました。
初期の投資コストはかなり必要になってきますが、どの分一気にサービスを作り上げて、顧客を取り囲んでしまうと、他社が追いつくまでに時間がかかるので、自分たちのサービスの寿命を一気に伸ばすことができるようになります。
3つ目は、上場させる、誰かに売却してExitしてしまう方法です。(その後勝ち残るかは不明ですが。。。)
今絶賛話題沸騰中のWeWorkなどはこの方法を取ろうとしていたのでは、と言われております。まだこの方法でSoftbankに売り渡して自分たちは逃げ切れると考えているかもしれません。
この方法は実際多くあり、エンジェル投資家などに投資を募り、ある程度サービスが軌道に乗ると、別の事業会社や投資家に売ってしまいます。
サービスが真似されて、より低価格で販売されるようになると、すぐに採算が合わなくなり、サービスを買い取った事業者は痛い目を見ることになります。
結局は固定費が膨らんでサービス継続が難しくなる
1つのサービスを継続することを考えると、開発コストが増えていくことは、サービスの収益を圧迫させることに直結します。
固定費には様々ありますが、やはりいちばん大きな部分は開発にかかる人件費です。
その他にも、サーバ代などもありますが、ユーザが増えるに応じてサーバスペックを適切に増やすことができれば、そこは大きな問題にならないでしょう。
開発をすすめると人件費がどんどん膨らみます。更に、それらの人材を管理したりプロジェクトを管理するコストも増え、人に求める能力もどんどん増えていきます。
そうなりますと、コストが膨大になり、最終的にはユーザ数も限界を迎え、採算が合わなくなるのです。
組織で開発するとこのような状況になることが予測できていまいます。
もちろん、今運用がうまくいっているサービスは、効率的に運用することで少ない人数で運用し、採算が取れているのだとは思います。(おそらく)
これからは個人でもサービス開発して事業を回すことができる
今はいろんなサービスが溢れています。競争がどんどん激化していっていますが、逆にサービスが溢れている今だからこそ、個人でのサービス運用が可能になってきました。
個人でのサービス開発をすることで、固定費などはサーバの代金程度で、ほとんど発生してきません。
もちろん、その分サービスのレベルは低くなってきます。
しかし、多くのITサービスは、本格的に運用に乗るまでは、ほとんど顧客対応などにリソースを割くよりは、サービスをどんどん開発したほうが価値はあがっていくことが多いです。
これからは、個人でサクッと色々と開発して、その後開発したものをビジネスでチームにしていくことがどんどんより流行っていくと考えられます。
今回の記事は以上です!
面白かったら是非シェアしてください!
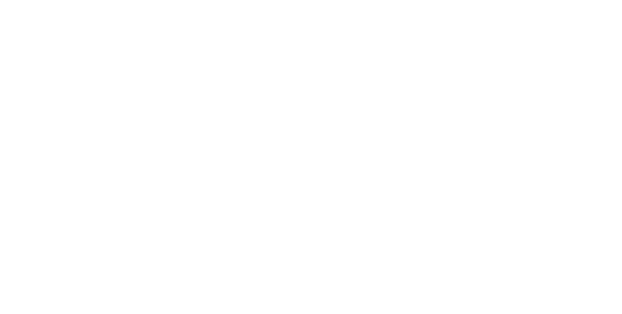

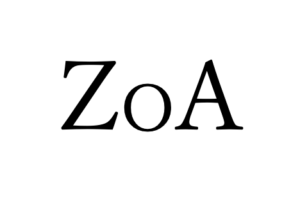





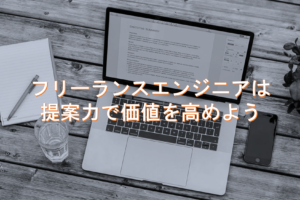


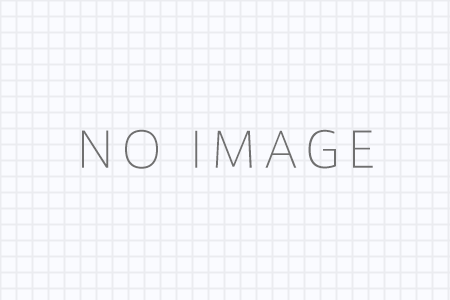
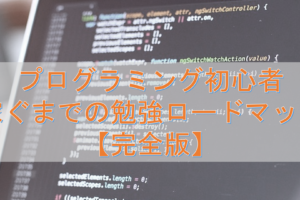
コメントを残す