こんにちは。ZOAMONです。
今回の記事では、アフターコロナの世界、つまり、今回のコロナ騒動が落ち着いてきた状態で、ビジネスはどのように変わっていくのか、をやっていきたいと思います。
騒動前から言われていたチャイナリスクとは?
これまで、コロナ騒動が起きる前は、チャイナリスクとは一体何だったのでしょうか?
以下の記事で話されているように、
・現地の人件費高騰などによる「コスト高」
・安価製品との競合による「価格競争」
であったと言われています。
https://moneyzine.jp/article/detail/216861
これは、中国の経済が成長して、コスト高になっていくことや、多くの企業が中国に生産拠点をおくことでより安く生産をすることで価格競争が激化する、などが言われておりました。
しかし、これらはこういうことが起きるまで、予測が可能なものでした。
中国の経済動向や、参入している企業がどれくらいいるのかなどのデータを見れば、現状はどの程度かわかりますし、後どれくらいは中国を生産拠点としてみることができれば、わかったのです。
コロナ騒動後にチャイナリスク認識を改められたのか?
しかし、今回の騒動は、予測不可能なものでした。
中国が流通サプライチェーンの単一障害点になっていることが露見されましたが、この予測不可能な状況に全く対応できる状態ではありませんでした。
これはどういうことかといいますと、生産拠点を価格や流通などの問題で、中国でほとんど行っている場合、今回のように中国で動けない状況になると、いち早くその企業の生産は停止してしまった、ということです。
店舗からは品物がなくなり、中国での生産も中止してしまったので、最終製品としては中国以外の国であっても、部品などが中国から入ってこなければ、最終製品も作ることができないという状況に陥ってしまいました。
今回は、結果的には経済全体が止まってしまったので、ものを作る必要がない状態になってしまいましたが、1月末や2月の段階の、「中国だけが止まってしまった状態」においては、作れば売れていた状態であったにも関わらず、作れずに、売ることができなかったという問題が発生している企業もありました。
多くの企業はこのリスクを甘く見ていた
しかし、これは本当に企業としては考慮できていなかったのでしょうか?
大企業の経営者たちがそんなことを考えることができなかったのかというと、そうではありません。絶対に、中国が単一障害点になっていたことはわかっていたはずです。
では、何故このリスクに対応できていなかったのでしょうか?
ここには、リスクと対応コストの比較の問題があります。これは、生命保険などの保険などと同じ問題です。
生命保険などに加入するとき、どのように加入を判断して入るのでしょうか?
それは、自分に万が一のことがある確率と、加入することで得られる補填金額、この2つを掛け合わしたものに、自分に万が一があったときに発生する損失を足し合わせた金額と、加入することで発生する費用を比較することになると思います。
「万が一トラブル発生確率×(補填金額+損失) >=< 保険費用」
これは、チャイナリスクに対応するかどうかを決める上でも、全く同じ計算式を使うことができます。
チャイナリスク発生確率×(補填金額+損失)>=< チャイナリスク対応費用
ここで、チャイナリスクの発生確率が、今回の騒動のように全く予測できないものであるとしましょう。
つまり、中国全体が止まることなどはほとんどないであろう、と考えられるときです。
その時は、チャイナリスク発生確率が0になります。
結果的に、チャイナリスク対応費用よりも、対応することで得られる金額の方が、少なくなってしまい、対応費用が無駄にかかる、という結論になるのです。
多くの企業は、このことから、チャイナリスクを甘く見ていたということです。
今後どうなっていくのか?
それでは、今後はどうなっていくのでしょうか?
今回の騒動で、チャイナリスク発生確率は0ではないことが明らかになりました。また、今後はこのようなことがいつ・どこで起きるのかわかりません。
今回のように、ウィルスで同じようなことが起きてしまうのか、もしくは戦争やテロなどの人的なもので起きてしまうのか、全くわかりません。
しかし、企業はこのようなリスクにも対応してビジネスを継続していく必要があり、対応できない企業は潰れていくだけですので、大きくビジネスの形は変わっていくと思います。
チャイナリスク対応は簡単ではない
ただ、このように言うことは非常に簡単ですが、実際はかなり難しい問題です。
生産拠点を複数置くことも、それに見合った利益を得ることができなければ、実現するだけコストがかさむだけということになりますし、そう沢山中国と同じようなコストや規模のメリットが得られる生産拠点があるわけでもありません。
また、物流においても、同じことが言えますので、生産拠点が複数あっても物流において単一障害点があったら、リスクに対応できているとは言えません。
ですので、今後企業がこのようなリスクにどう対応していくのか、非常に注目するポイントです。この動向を見ておくと、それに乗って次のビジネスを考えることができるかもしれません。
最後に
いかがでしたでしょうか?
今回は、このコロナ騒動を受けて、次何を考えられるのか、「チャイナリスク」という点から考えられることをブログ記事にしてみました。
少しでも、参考になることができたら嬉しいです!
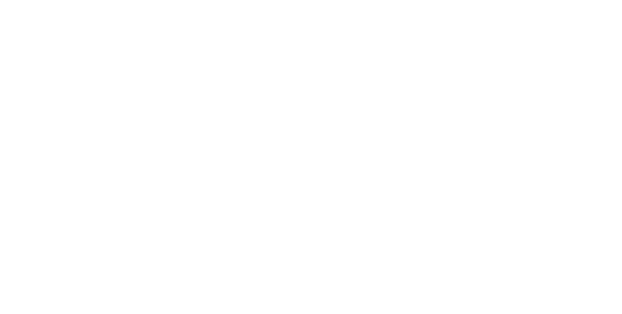

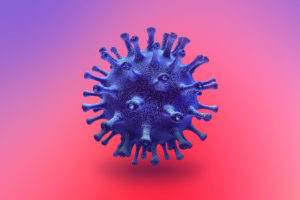
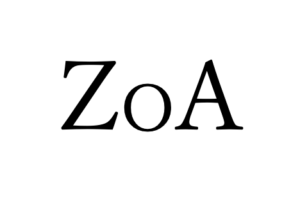


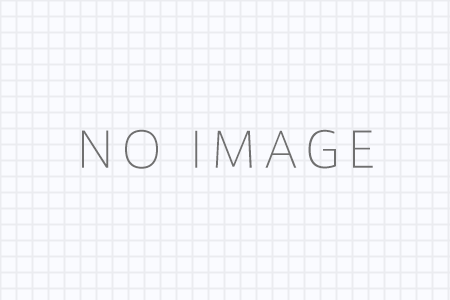
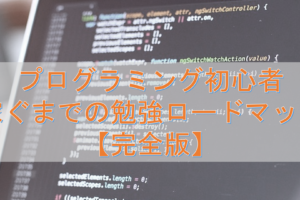
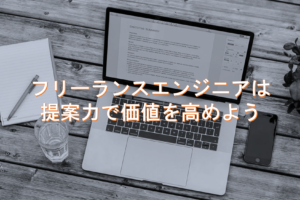

コメントを残す